 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
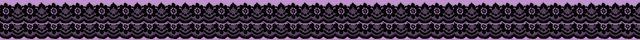
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
真夏の悪夢
第3章 夢の膨らむ思春期、青春時代
昭和40年(1965年)、時代は東京オリンピックを境に大きく変わっていく。
小枝子の住む町でも田畑は宅地に変わり、アパートや建売住宅が次々と建てられ、住む人たちも多くなった。
「化粧なんかして、色気づいて」
4月、高校3年生になった小枝子は母親の化粧品を使い、初めてお化粧をしたが、母親に小言を言われてしまった。
「だって、お母さん、就職試験で『変な顔している』って言われたら、困るじゃない」
「バカなことを言うんじゃないよ。女は昔から『マメで、達者で、元気よく』って言うんだよ。色気があって喜ばれるのは女郎だけ」
「だけど、友だちはみんなお化粧の練習をしているわよ。」
「そうかね。学校の先生に叱られたら、泣くのはお前だよ」
「お母さんは古すぎるのよ」
小枝子はそう言ったが、学校で化粧が許される筈がない。だが、商業高校故、卒業生の大半は就職する。特に身近な存在だった1学年上の先輩たちが華やかに化粧をしているのを見れば、年頃の女の子は、いつの時代も背伸びしたくなるもの。
しかし、母親が本当に心配していたのはそんなことではなかった。小枝子の背丈は160cmと当時の女の子としては大柄、それに、胸は85cm、腰が62cm、お尻は86cm、古い言葉で言えばグラマーだ。否が応でも目立つ。それに化粧なんかしたら、男たちにイヤらしい目で追い回されるのが目に見えていた。
変な噂でも立てられたら、嫁入り話が来なくなってしまう。
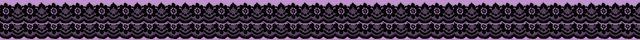
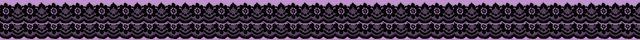
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


