 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
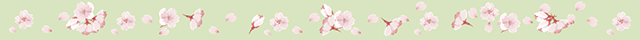
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
降りしきる黄金の雫は
第12章 12 香り
春の訪れを知らせてくれる沈丁花の香りが漂い始めた。この花は初夏に咲くクチナシと秋に咲く金木犀と並んで三大香木と言われる。
また金木犀と同じく中国から室町時代に日本へ伝わったようで更には雌雄異株の上、日本には雄株しかないところまで共通している。
桂さんに出会うまでは『良い香り』だと思うだけだったが、共通点の多さに親しみを覚える。そしてもしも沈丁花が桂さんのように擬人化したらどうなるのかと想像した。
「中国名で瑞香かな……」
ぼんやり春の陽気と香りを楽しんでいると、その香りを覆いつくすようにより甘い香りが漂う。
「あっ、桂さん。こんな時間に珍しいですね」
「それは浮気というものか?」
「え!? や、やだなあ、違いますよ」
少し笑んだ桂さんは随分柔らかい物腰になってきている。するっと音もなく近づき、僕の横に座って一緒に沈丁花の香りを嗅いだ。
「いい香りだ。私たちの古くからの友人だ。香りが重ならないように季節をずらしている」
「へえー。確かにかぶっちゃうともったいないですよね」
山吹色の伏せられたまつ毛の影が桂さんの眼差しをより美しくする。
「私ではなく、彼らと先に出会っているかもしれなかったな」
「もうっ!桂さん、意地悪を言わないでください!」
「ふふ。悪かった」
「僕は、金木犀の香りが一番好きですよ。沈丁花の次にクチナシが香って、秋になると金木犀。待ち遠しいです」
彼の手がふわりと伸びて、僕の頭を膝へ乗せ、髪を撫でる。心地よさにうっとりしながら、沈丁花の英名がダフネだったことを思い出す。
「ねえ、桂さん。人間は植物になれるとおもいますか?」
「さあな」
「ギリシャの神話にダフネという人間の娘が月桂樹の木になる話があるんです」
「なぜ、木になったのだ」
「――嫌いな神からの求婚を逃れるためだったかな」
「そうか」
なんとなく悲しい話をしてしまったことを後悔したが甘い香りと小春日和の陽気に瞼が重くなった。
また金木犀と同じく中国から室町時代に日本へ伝わったようで更には雌雄異株の上、日本には雄株しかないところまで共通している。
桂さんに出会うまでは『良い香り』だと思うだけだったが、共通点の多さに親しみを覚える。そしてもしも沈丁花が桂さんのように擬人化したらどうなるのかと想像した。
「中国名で瑞香かな……」
ぼんやり春の陽気と香りを楽しんでいると、その香りを覆いつくすようにより甘い香りが漂う。
「あっ、桂さん。こんな時間に珍しいですね」
「それは浮気というものか?」
「え!? や、やだなあ、違いますよ」
少し笑んだ桂さんは随分柔らかい物腰になってきている。するっと音もなく近づき、僕の横に座って一緒に沈丁花の香りを嗅いだ。
「いい香りだ。私たちの古くからの友人だ。香りが重ならないように季節をずらしている」
「へえー。確かにかぶっちゃうともったいないですよね」
山吹色の伏せられたまつ毛の影が桂さんの眼差しをより美しくする。
「私ではなく、彼らと先に出会っているかもしれなかったな」
「もうっ!桂さん、意地悪を言わないでください!」
「ふふ。悪かった」
「僕は、金木犀の香りが一番好きですよ。沈丁花の次にクチナシが香って、秋になると金木犀。待ち遠しいです」
彼の手がふわりと伸びて、僕の頭を膝へ乗せ、髪を撫でる。心地よさにうっとりしながら、沈丁花の英名がダフネだったことを思い出す。
「ねえ、桂さん。人間は植物になれるとおもいますか?」
「さあな」
「ギリシャの神話にダフネという人間の娘が月桂樹の木になる話があるんです」
「なぜ、木になったのだ」
「――嫌いな神からの求婚を逃れるためだったかな」
「そうか」
なんとなく悲しい話をしてしまったことを後悔したが甘い香りと小春日和の陽気に瞼が重くなった。
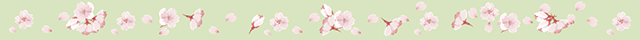
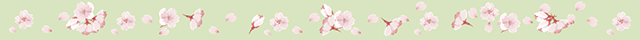
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


