 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
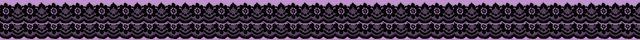
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
担当とハプバーで
第2章 危険な好奇心
パラリと開いたメニューに顔を近づける。
ハヤテが長い指でとん、とヴーヴを指差す。
一万五千円だ。
全部のメニューを覚えているわけじゃないので、サーっと視線が散ってしまう。
「俺が来る前にメニュー見てるとは思うけど、今度から酒の種類じゃなくて酒の名前で教えて」
「わかった」
「例えば」
そこで話題は終わらせんよ、と口調が強まる。
「焼酎な。このエリア見て。好きなのどれ」
「黒か梅酒」
「うん。前に黒霧島好きって言ってたと思うから今頼んだけど、下は五千から上は十万まである」
十万のは聞いたこともない銘柄。
「で、次シャンパンね。ホストといえばシャンパンってくらいにメジャーだけど種類もすごい多い。このエリア全部」
一応目は通したけれど、改めて見ると値段差がすごい。
桁が三桁違うのまである。
ハヤテがメニューをテーブルに戻して、腿に肘をついて頬杖をしつつ、じっと見つめてくる。
「凛音も来てくれんの三回目。適度に楽しんでほしいから、ちゃんと値段見てちゃんと飲みたいもん教えて」
言いたいことがわかってシュンとしてしまう。
本来は来る前に学ぶべきことを、ホストに言わせてしまっている状況が心にくる。
「知ってると思うけど、掛けって制度もある。でも無理はして欲しくないし、俺はナンバー入ってるから困ってもない。凛音がガチで俺が最初のホストなんかなって思うし、紹介で来たわけでもないから慣れてもないだろ」
「はい……」
「これからも来てほしいから、今だけ口うるさいホストになりました。おしまい。ほら、来たから乾杯しよ」
慣れた手つきで注がれたグラスを手に取り、揺れる氷を見てなんだか泣きたくなる。
ヴーヴは一番安い方のシャンパンだった。
それより三倍のを頼まれたってきっと何も言えなかっただろうし、気を遣わせたのがわかる。
コン、とグラスを合わせてからも、いつもより喉を焼く味になんだか消えたくなってくる。
「凛音」
呼ばれて顔を上げると、思っていたより目の前にハヤテの顔があって、固まってしまう。
「楽しくなくなっちゃった?」
「ううん……私馬鹿だなあって思って」
髪を耳にかけながら、目を背ける。
するとそっとその耳元に囁かれた。
「俺のために好きなもん飲ませようって思ってくれたんだろ。ありがと」
イヤホンよりも間近での低音に全身が痛いくらい喜びに満ちた。
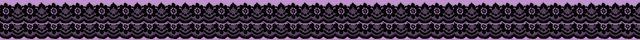
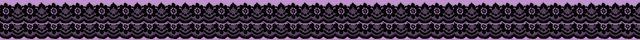
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


