 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
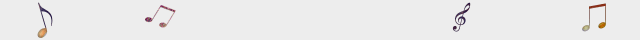
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
痴漢脳小説2 ~ガールズバンドに男子の僕が入っちゃいました~
第6章 『仲間』
「寒いのね」
来客用のソファーのいつもの位置に腰を落ち着けてイズミさんが言った。
「はい」
「暖房は?」
「一人の時はちょっと…使いにくくて」
うん、とイズミさんは頷いてリモコンをエアコンに向けた。
「つけたのは私だから」
暖かい風が流れてきて、でもそれ以上にイズミさんがそこにいることに安心を覚える。
安心? イズミさんに?
だいぶ雪解けしたとはいえ、僕はイズミさんが苦手、とか思っていなかったっけ?
それでもあの夜のことを思い出しておかずにしているんだから、僕ってやつは本当は痴漢とかそんなの関係なくただのスケベ野郎なんじゃないのかって、ちょっと自分を疑う。
「仕事終わりなの」
「え…ああ、お疲れ様です。あ、何か温かい飲み物でも」
ケトルには水が入りっぱなしだ。スイッチを入れればすぐに沸くはずだ。
「最後のお客さんが延長して。それでこんな時間になっちゃった」
イズミさんの仕事はデリヘルだ。それを知っているから僕は上手く言葉が選べない。イズミさんも口数が少ないから二人っきりになるのはちょっと困る。
二人っきり、といえばあの駐車場での出来事を思い出してしまうし。
…やっぱり僕ってただのスケベ野郎?
「これ」
マグカップとインスタントのティーバッグ、砂糖とミルク。それらを持って戻るとそれを待っていたかのようにイズミさんは鞄から出した封筒を僕のほうへとテーブルの上を滑らせる。
その封筒の中身は一万円札。
それも一枚や二枚じゃない。厚さからしておそらく百万円…
僕が困惑しているとカチっと音がしてケトルの中でお湯が沸いた。イズミさんはマグカップを引き寄せティーバッグを落とし、お湯を注ぐ。
「あ、あの…これ」
「受け取って。生活の足しにして」
「だけど…こんなにたくさん」
マグカップから湯気が立ち上り、エアコンの風が吹き流す。
「ちょっと温度高いみたいね」
細く長い指がリモコンをつまみ、ピっと音をさせた。
僕はただただ、それを見ていた。
暖かい風を送り出すエアコンとそれを操るイズミさんと、温かい紅茶と目の前に置かれた一万円札の束とを。
イズミさんは熱い紅茶を啜るようにして一口飲んだ。
来客用のソファーのいつもの位置に腰を落ち着けてイズミさんが言った。
「はい」
「暖房は?」
「一人の時はちょっと…使いにくくて」
うん、とイズミさんは頷いてリモコンをエアコンに向けた。
「つけたのは私だから」
暖かい風が流れてきて、でもそれ以上にイズミさんがそこにいることに安心を覚える。
安心? イズミさんに?
だいぶ雪解けしたとはいえ、僕はイズミさんが苦手、とか思っていなかったっけ?
それでもあの夜のことを思い出しておかずにしているんだから、僕ってやつは本当は痴漢とかそんなの関係なくただのスケベ野郎なんじゃないのかって、ちょっと自分を疑う。
「仕事終わりなの」
「え…ああ、お疲れ様です。あ、何か温かい飲み物でも」
ケトルには水が入りっぱなしだ。スイッチを入れればすぐに沸くはずだ。
「最後のお客さんが延長して。それでこんな時間になっちゃった」
イズミさんの仕事はデリヘルだ。それを知っているから僕は上手く言葉が選べない。イズミさんも口数が少ないから二人っきりになるのはちょっと困る。
二人っきり、といえばあの駐車場での出来事を思い出してしまうし。
…やっぱり僕ってただのスケベ野郎?
「これ」
マグカップとインスタントのティーバッグ、砂糖とミルク。それらを持って戻るとそれを待っていたかのようにイズミさんは鞄から出した封筒を僕のほうへとテーブルの上を滑らせる。
その封筒の中身は一万円札。
それも一枚や二枚じゃない。厚さからしておそらく百万円…
僕が困惑しているとカチっと音がしてケトルの中でお湯が沸いた。イズミさんはマグカップを引き寄せティーバッグを落とし、お湯を注ぐ。
「あ、あの…これ」
「受け取って。生活の足しにして」
「だけど…こんなにたくさん」
マグカップから湯気が立ち上り、エアコンの風が吹き流す。
「ちょっと温度高いみたいね」
細く長い指がリモコンをつまみ、ピっと音をさせた。
僕はただただ、それを見ていた。
暖かい風を送り出すエアコンとそれを操るイズミさんと、温かい紅茶と目の前に置かれた一万円札の束とを。
イズミさんは熱い紅茶を啜るようにして一口飲んだ。
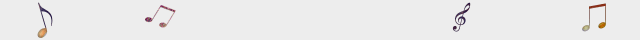
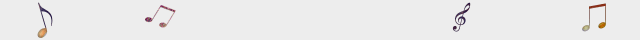
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


