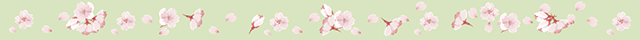
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
恋いろ神代記~神語の細~(おしらせあり)
第2章 桂楫
月読は優沙のすがるような眼差しにも声にも応えず、代わりにゆっくりと跪くと留めた手を取り、その赤黒く腫れた甲にそっと唇を捧げた。
途端に背後で、二つの気配がそわつく。優沙にもそれが何であったのか、すぐさま理解することができた。
けれども優沙は、もうそれにも邪(よこしま)な感傷を持つことはできなかった。安堵も、感謝も、まだ何も持てなかった。
しかし月読もまたそれを承知のように何も語らず、求めず、体を起こして横に一歩を退くと、ようやく優沙に視界を明け渡す。
見慣れていたはずの庭は、今や別世界のように月の光に照らされて不思議な色を宿していた。天から頂戴した、朧の色。
絶えていたはずの池の水の音も蘇り、元々細やかではあったが、泥に覆われていた流れの筋がきらきらと横に動いている。
もうあの恐ろしい蜂の群れもおらず、優沙はまるで夢でも見ていたかのような不可思議な心地になって、静かで穏やかな、懐かしい夜の姿をぼうっと見つめた。
血糊のような花弁も、斬り首のような花も何もない……。ただ残されていたのは、さやさやと夜を揺らす風に身を任せ、揺りかごに揺られる赤子のように無防備に眠りについた……小さな赤い花の、たくさんのつぼみだけ。
途端に背後で、二つの気配がそわつく。優沙にもそれが何であったのか、すぐさま理解することができた。
けれども優沙は、もうそれにも邪(よこしま)な感傷を持つことはできなかった。安堵も、感謝も、まだ何も持てなかった。
しかし月読もまたそれを承知のように何も語らず、求めず、体を起こして横に一歩を退くと、ようやく優沙に視界を明け渡す。
見慣れていたはずの庭は、今や別世界のように月の光に照らされて不思議な色を宿していた。天から頂戴した、朧の色。
絶えていたはずの池の水の音も蘇り、元々細やかではあったが、泥に覆われていた流れの筋がきらきらと横に動いている。
もうあの恐ろしい蜂の群れもおらず、優沙はまるで夢でも見ていたかのような不可思議な心地になって、静かで穏やかな、懐かしい夜の姿をぼうっと見つめた。
血糊のような花弁も、斬り首のような花も何もない……。ただ残されていたのは、さやさやと夜を揺らす風に身を任せ、揺りかごに揺られる赤子のように無防備に眠りについた……小さな赤い花の、たくさんのつぼみだけ。
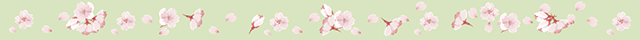
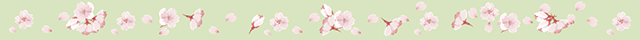
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く



