 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
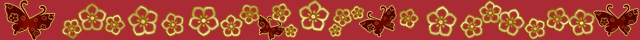
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
安田博の性犯罪録
第1章 女子大生・吉田さやか 1
安田はさやかのその言葉にさらに興奮した。この若い極上の女の処女を好きにできるのだ。
いくら大金をつぎ込んでも不可能だろう。8年間刑務所で我慢した神様からのご褒美だ!
罪を償うといったそういう考えは毛頭なく、安田は本気でこう思っていた。
安田は次に、さやかをベッドの上に座らせ、自分もその横にピッタリと座り、横から両手で乳房をまさぐりながら質問攻めにした。
さやかは既に完全に安田の支配下に置かれ、抵抗することも嘘をつくことも諦めていた。
安田の言われるがまま、初恋はいつだったのか、いつからブラジャーしたのだとか、そういったことを答えていた。
なんで女子高に行こうと思ったの?
それまで一言でしか返答しなかったさやかが、この質問には文章にすれば数行に達するほどの長さで答えた。
さやか自身にも何故だかわからなかった。
「中学3年生のとき、隣の男のことが好きだったんですけど…なんだかそのことが
クラスの男子の間で噂になって…他の男子にずっとからかわれたんです。
おれにも見せろ、とか言われてスカートめくられたりとか…
それで男子が嫌いになって女子高に進学しようかなって…」
スカートめくられたぐらいで嫌いになるなら、パンツ一枚にして胸を揉んでるおれはどうなるんだろうな。安田は思った。
そしてさやかの中学時代の姿を頭の中で思い描き、スカートをめくることしかできなかった男子中学生に対して優越感を抱いていた。
そしてふと、安田も自分の中学時代のことを呟いた。
「おれも中学時代は女に嫌われていたな。勉強もスポーツも容姿も何もかもダメだったからな。
だからこういう反社会的な極道の道に進むしかなかった。」
正確に言えば、極道の道からもすぐ逃げ出したけどな。安田は心の中で呟いた。
斜め下を向いて俯きながら、ずっとされるがままにされていたさやかは、
自分のことをふと語りだしたこの男に、ほんの少しばかりの親近感を覚えていた。
さやか自身もこの自分の感情に驚いていた。
その感情を覚えた理由は、ストックホルム症候群と呼ばれているものの始まりであるということを、その時の彼女が知る術はなかった。
いくら大金をつぎ込んでも不可能だろう。8年間刑務所で我慢した神様からのご褒美だ!
罪を償うといったそういう考えは毛頭なく、安田は本気でこう思っていた。
安田は次に、さやかをベッドの上に座らせ、自分もその横にピッタリと座り、横から両手で乳房をまさぐりながら質問攻めにした。
さやかは既に完全に安田の支配下に置かれ、抵抗することも嘘をつくことも諦めていた。
安田の言われるがまま、初恋はいつだったのか、いつからブラジャーしたのだとか、そういったことを答えていた。
なんで女子高に行こうと思ったの?
それまで一言でしか返答しなかったさやかが、この質問には文章にすれば数行に達するほどの長さで答えた。
さやか自身にも何故だかわからなかった。
「中学3年生のとき、隣の男のことが好きだったんですけど…なんだかそのことが
クラスの男子の間で噂になって…他の男子にずっとからかわれたんです。
おれにも見せろ、とか言われてスカートめくられたりとか…
それで男子が嫌いになって女子高に進学しようかなって…」
スカートめくられたぐらいで嫌いになるなら、パンツ一枚にして胸を揉んでるおれはどうなるんだろうな。安田は思った。
そしてさやかの中学時代の姿を頭の中で思い描き、スカートをめくることしかできなかった男子中学生に対して優越感を抱いていた。
そしてふと、安田も自分の中学時代のことを呟いた。
「おれも中学時代は女に嫌われていたな。勉強もスポーツも容姿も何もかもダメだったからな。
だからこういう反社会的な極道の道に進むしかなかった。」
正確に言えば、極道の道からもすぐ逃げ出したけどな。安田は心の中で呟いた。
斜め下を向いて俯きながら、ずっとされるがままにされていたさやかは、
自分のことをふと語りだしたこの男に、ほんの少しばかりの親近感を覚えていた。
さやか自身もこの自分の感情に驚いていた。
その感情を覚えた理由は、ストックホルム症候群と呼ばれているものの始まりであるということを、その時の彼女が知る術はなかった。
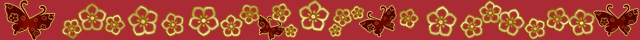
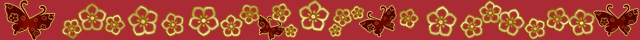
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


