 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
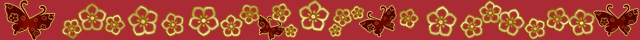
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
安田博の性犯罪録
第1章 女子大生・吉田さやか 1
さやかの父親は、地元の国立大学で大学教授をやっていた。そして、とても厳格な父親だった。
子供の教育とは、子供を厳しく律することであり、それによって正しい人格が育つという考えの持ち主だった。
その教育方針は、いかんなくさやかに対して発揮され、少しでも気に入れないことがあると、容赦なく幼いさやかを怒鳴った。
幼少のさやかは、父親に怒鳴られるたびに自分の思いを押し殺すようになった。
そして同時に、父親の顔色を窺う術を身に付け、常に父親が何を望んでいるかを必死に考えるようになった。
さやかが小学生5年生のころだった。その当時、さやかのクラスの女子の間でバレンタインデーのお菓子を作ろうという話が出ていた。
お菓子を作って男子に配りお返しを期待するとか、女子同士で分け合うとか、そのような他愛もない目的だった。
中には、こっそりと好きな男子に渡そうとする女子もいた。
料理をすることが好きだったさやかは、特段好きだった男子もいなかったが、喜んでその話にのることにした。
そしてバレンタインデーの前日、母親と相談し、さやかはクッキーを焼くことにした。
「まだそういうことは早い」
仕事から帰ってきてその姿を見た父親は、さやかに向かってそう言った。
そして、さやかの目の前で、母親を怒鳴り散らした。
何をやらせてるんだ、その年で色気付かせてどうする、と。
小学5年生のさやかには、色気付かせるという台詞の意味がよくわからなかった。
ただ母親は必死に「これは女の子同士で分け合うためのものです」と弁明していた。
さやかはその時に悟った。男に対して特別な感情を持つことは悪いことである、と。
お洒落をすること、化粧をすること、少女漫画を読むこと、男子を好きになること。
さやかの家では、それは悪いことであり、父親の機嫌を損ねることであった。
母親もその父親の教育方針に従い、さやかに女の子らしいことをすることを許さなかった。
私が今こんなことになっていると知ったら、お父さんとお母さんどう思うかな
さやかの中に、恐怖、罪悪感、背徳感、そしてその中に両親に対する反抗心が芽生えていた。
私はこんなことされてるよ。でも仕方がないもの
子供の教育とは、子供を厳しく律することであり、それによって正しい人格が育つという考えの持ち主だった。
その教育方針は、いかんなくさやかに対して発揮され、少しでも気に入れないことがあると、容赦なく幼いさやかを怒鳴った。
幼少のさやかは、父親に怒鳴られるたびに自分の思いを押し殺すようになった。
そして同時に、父親の顔色を窺う術を身に付け、常に父親が何を望んでいるかを必死に考えるようになった。
さやかが小学生5年生のころだった。その当時、さやかのクラスの女子の間でバレンタインデーのお菓子を作ろうという話が出ていた。
お菓子を作って男子に配りお返しを期待するとか、女子同士で分け合うとか、そのような他愛もない目的だった。
中には、こっそりと好きな男子に渡そうとする女子もいた。
料理をすることが好きだったさやかは、特段好きだった男子もいなかったが、喜んでその話にのることにした。
そしてバレンタインデーの前日、母親と相談し、さやかはクッキーを焼くことにした。
「まだそういうことは早い」
仕事から帰ってきてその姿を見た父親は、さやかに向かってそう言った。
そして、さやかの目の前で、母親を怒鳴り散らした。
何をやらせてるんだ、その年で色気付かせてどうする、と。
小学5年生のさやかには、色気付かせるという台詞の意味がよくわからなかった。
ただ母親は必死に「これは女の子同士で分け合うためのものです」と弁明していた。
さやかはその時に悟った。男に対して特別な感情を持つことは悪いことである、と。
お洒落をすること、化粧をすること、少女漫画を読むこと、男子を好きになること。
さやかの家では、それは悪いことであり、父親の機嫌を損ねることであった。
母親もその父親の教育方針に従い、さやかに女の子らしいことをすることを許さなかった。
私が今こんなことになっていると知ったら、お父さんとお母さんどう思うかな
さやかの中に、恐怖、罪悪感、背徳感、そしてその中に両親に対する反抗心が芽生えていた。
私はこんなことされてるよ。でも仕方がないもの
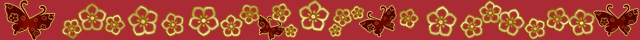
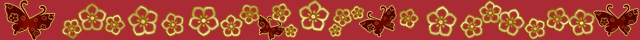
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


