 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
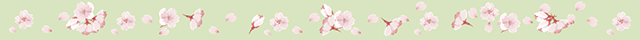
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
胸懐の本棚
第1章 胸懐の本棚
夜には意識レベルが低下し、昏睡状態に陥った。
ときおり喉の奥にうわ言を絡めたが、哲夫が耳を近づけても、意味をなす言葉にはなっていなかった。
呼吸の間隔が長くなり最後の息を吐くまでの間、滅んでいく美里を見つめ続けながら、哲夫は、この世界もろとも何もかも終わってしまえばいいと思った。
美里を喪ったあとも、自分は死ぬまで生きなければならない。
その苦痛と恐怖に耐える力を自分のどこにも見つけられなかった。
葬式を終えて初七日が過ぎ、四十九日を迎えても、美里のいない時間は地を這うようにゆっくりと進んだ。
「もし美里が生きとったら」と、「もう美里は死んでしもた」を考えない日はなかった。
考え始めると、やがて何ものにも期待できなくなって、すべてが無価値だと思えてくる。
見渡すかぎり心を動かすもののないどこかの星に、ぽつんとひとり置かれたような虚無感が哲夫の心を統べた。
八畳間の天井を破って二階の梁にロープをまわしたのは、まさにそんなときだった。
深夜、哲夫は憑かれたように天井板を破壊した。
踏み台につま先立って梁へロープを掛け、片方の端を輪っかに括って首に巻いた。
見おろすと、写真立ての美里がほほえみかけていた。
固く目を閉じて踏み台を蹴る。
耳の奥に聞いたことのない音を聞き、ロープが喉に食いこむと同時に足元が軽くなり、哲夫はつかのま宙吊りになった。
煮え立つような苦しさで反射的にロープを掴もうともがくも、喉を絞めるロープに指を通す余地はなく、足だけが宙にばたついた。
部屋が回りはじめ、全身が脱力し、泡沫状の唾液が口辺から溢れ、背骨が伸びきり、胸元で体が上下にちぎれていく感覚だけになった。
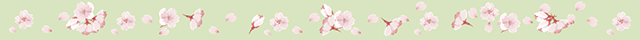
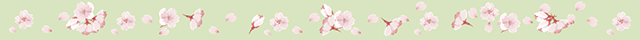
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


