 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
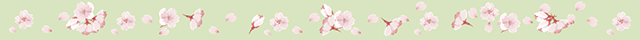
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
胸懐の本棚
第1章 胸懐の本棚
真紀がこれほど多くの言葉を連ねて心情を語ったのは初めてだった。
どうして彼女はそんな話をしたのか。特に最後の言葉を、哲夫は自分と無関係に聞くことができなかった。
『生きてる人間が底なしの穴へ、かぁ……』
復唱したあと、哲夫は唸りの混じった息を吐いた。
応じ返すのが難しい話だと思ったのか、そこでようやく、真紀は微苦笑を見せた。
『滅入るような話ですみません』
『いや、そんなことないで。
生きてる人間が底なしの穴へ。なぁ……』
哲夫にそれ以上の言葉が浮かばなかったのは、実に的確な表現だと感嘆したからである。
人間から希望を奪う穴。幸福を絶望に変える穴。
真紀が感じた得体の知れない恐ろしさがどういうものであるのか、哲夫にはわかる。
警察から電話がかかってきたときの、命を搾られるような出来事を前にして途方にくれている高田家の様子や、しかるのちに病院へ向かう車中のありようが、まるで同じ車に乗り合わせているかのように想像できた。
押し黙って運転する父親は空洞のような眼で正面を見据え、その後部座席で怯えた真紀が握りしめる母親の手も、また震えていたことだろう。
真紀は身内の死より、その死によって自分にもたらされるものに恐怖を感じた。
身内に迫る死に眼を瞠(みは)り、厄難を受けいれるまでの混沌。
その得体の知れない不快感の中に、人は不幸を見る。
同じものを哲夫も見てきた。
「生きてる人間が底なしの穴へ引きずられていくような」、という真紀の言葉は、美里を喪くしたあの頃の、誰にも理解されなかった哲夫の生き難さそのものを、見事に言い当てていた。
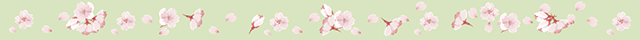
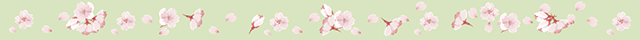
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


