 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
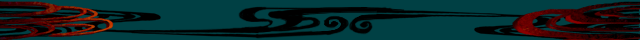
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
姫巫女さまの夜伽噺
第3章 儀式
(名器? どう言うこと?)
穂高の声に
意識を持っていかれそうになった瞬間
志摩の声が脳内を揺さぶる。
『穂高は無視しろ。
愛蘭、今お前に聞こえるのは俺の声だけだ』
「え…?」
その瞬間
外部の音が遮断された。
『そうだ、良い子だ。
もう、痛くないだろ?』
志摩の口づけは止まず
体中が熱くなるのを感じる。
痛くない、と志摩の声を頭の中で復唱すると
下腹部の鋭い痛みが和らいだ。
(まさか、呪禁って…)
意識が現実に戻ろうとするのを
志摩の舌が許さない。
たっぷりの唾液を含ませた潤沢な舌が
愛蘭の思考を根こそぎ取っ払うかのように重なる。
『愛蘭、その痛みは、すでにもう快楽へと変わっているだろう?』
志摩の、脳内に直接響く声が聞こえる。
目を開ければ
黄金色の瞳と目が合った。
(快楽…?)
『交わる事、犯される事。
それはもう、お前にとって快楽でしかない。
そして、誇りになるはずだ』
志摩の独白だけが、愛蘭の脳に響く。
世界が切り取られる感覚。
ここには自分と志摩としか居ないのではないかと思われるほどの長い時間。
『こうして俺の舌を受け入れる事。
男に貫かれる事。
縛られたり、弄ばれたりする事。
敏感なところを責められる事。
全て、お前にとって、快楽だ。
どうしようもなく欲し
どうしようもなく愛おしくなる。
相手が誰であろうと、善がりまくる…』
志摩の独断的なしゃべりは続き
穂高がとか、痛みとか
そういった全てのものが消え去って行く。
頭の中は真っ白で何もなく
志摩の言葉だけが
白い脳内に秩序として書き込まれて行くかのような感覚。
不思議と怖くはなく
生まれ変わるってこう言う感じなのかななどと
呑気に考えられるほどに余裕があった。
しかし、その余裕に気づいてか
志摩が愛蘭に深く語りかけた。
『でもな、お前が一番感じるのは…
お前が一番善がり狂うのは…お前を助けた俺とだけだ』
志摩が口づけを一瞬離して
ふと笑った。
「え、志摩…なんで…」
愛蘭の疑問は
志摩の勝ち誇った笑みと
二人にしか聞こえない言葉によってかき消された。
『愛蘭、喘げ』
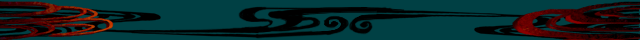
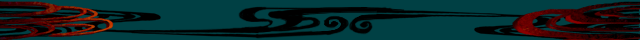
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


