 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
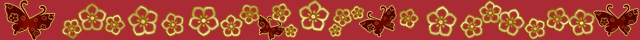
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
女鑑~おんなかがみ~
第11章 嗜虐
若槻は,料亭の豪華な料理を口に運びながら,姉と食事をしたのは幼い日以来であることを思い出した。
互いに大体の居場所を把握してはいたが,面と向かって食事をすることは,姉が置屋の養女となって以来で,四十年近く昔のことであった。
姉が京都で養女になったと父に聞かされた半年後,若槻は学校の遠足で京都に行った。
当時,若槻と最も仲の良かった友達の雅夫は,従兄が京都の料亭で板前の見習いをしているとかで,しばしば京都を訪ねており,遠足を引率する教師よりもはるかに詳しかった。遠足では寺社でも通りでも,雅夫が教師を差し置いて観光案内をするという始末だった。遠足の一行は,円山公園で弁当を食べた。
桜の木のふもとに,着物姿の男女が見えた。
「あそこに舞妓さんがいるよ。きれいだね」
何人かが声を上げて騒ぎ出した。
桜の木の下に,商人風と見える四,五十代の男たちが集まっており,その中に美しく着飾った女性が何人かいた。若槻は,そのうちの一人を見て声を上げそうになった。
白地に淡い紫の花柄がある着物を着た舞妓は,まさしく半年前に別れた姉だった。
若槻は,遠足中であることも忘れて駆け出した。
ほかの生徒たちは弁当を広げることに夢中であまり気づかないようだった。
息を切らして走り,「姉上さま,姉上さま」と呼びかけると,姉は確かに振り向いた。
振り向いて若槻の顔を見た姉は,途端に蒼白な表情になり,手で追い払うようなしぐさをした。
「もどりなさい。ここへきてはいけません」泣いたような声を振り絞ってそういうのが聞こえた。
立ち止まった若槻は,次の瞬間目を疑った。
美しい舞妓姿の姉は,横にいた男の羽織の袖に自分の顔を埋めて隠そうとしたのだ。
商人風のその男は,着物こそ何やら高級そうな生地のものを着ているが,どう見ても父親よりも年長で,ぎょろっとした目や張ったエラ,口元のイボがヒキガエルをほうふつとさせた。
互いに大体の居場所を把握してはいたが,面と向かって食事をすることは,姉が置屋の養女となって以来で,四十年近く昔のことであった。
姉が京都で養女になったと父に聞かされた半年後,若槻は学校の遠足で京都に行った。
当時,若槻と最も仲の良かった友達の雅夫は,従兄が京都の料亭で板前の見習いをしているとかで,しばしば京都を訪ねており,遠足を引率する教師よりもはるかに詳しかった。遠足では寺社でも通りでも,雅夫が教師を差し置いて観光案内をするという始末だった。遠足の一行は,円山公園で弁当を食べた。
桜の木のふもとに,着物姿の男女が見えた。
「あそこに舞妓さんがいるよ。きれいだね」
何人かが声を上げて騒ぎ出した。
桜の木の下に,商人風と見える四,五十代の男たちが集まっており,その中に美しく着飾った女性が何人かいた。若槻は,そのうちの一人を見て声を上げそうになった。
白地に淡い紫の花柄がある着物を着た舞妓は,まさしく半年前に別れた姉だった。
若槻は,遠足中であることも忘れて駆け出した。
ほかの生徒たちは弁当を広げることに夢中であまり気づかないようだった。
息を切らして走り,「姉上さま,姉上さま」と呼びかけると,姉は確かに振り向いた。
振り向いて若槻の顔を見た姉は,途端に蒼白な表情になり,手で追い払うようなしぐさをした。
「もどりなさい。ここへきてはいけません」泣いたような声を振り絞ってそういうのが聞こえた。
立ち止まった若槻は,次の瞬間目を疑った。
美しい舞妓姿の姉は,横にいた男の羽織の袖に自分の顔を埋めて隠そうとしたのだ。
商人風のその男は,着物こそ何やら高級そうな生地のものを着ているが,どう見ても父親よりも年長で,ぎょろっとした目や張ったエラ,口元のイボがヒキガエルをほうふつとさせた。
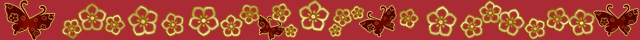
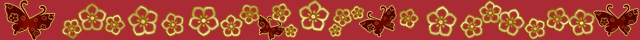
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


