 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
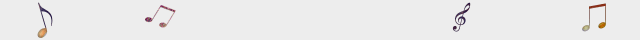
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
もうLOVEっ!ハニー!
第21章 眩さから逃げ出して
その笑顔の真意は測れませんでした。
ただ、それで流れてしまう話題でもなく、視線の束は私を逃してはくれません。
「どうなの? 華海都寮だもんね。引退試合前、二人きりで抜け出してたんでしょ」
確か、高水という苗字だった気がするその女子が椅子の隣に立っている。
その後ろに談笑していた女子が三人。斜め右手から江川の視線。
真後ろから恭平と倉場の興味に満ちた空気。
教室の中のざわめきが途絶えて、全員が聞き耳を立てているような鳥肌。
「その」
声がかすれてしまい、軽く咳をして唇を舐める。
その数秒に私は油断したんでしょうか。
彼女の指が横髪をふわりと持ち上げて、首に顔を近づけた。
そこは、ファンデで隠し切れない場所。
ばっと手を振り払う前にもう手は離れていました。
「すっご……」
ああ、感情の竜巻のような声。
急いで首元を両手で隠しても、彼女の表情が教室中に知らせていました。
「だから髪巻いておろしてたんだ?」
どっ、どっ、と遠くから聞こえる血流。
積もった雪に靴が濡れていくように足先が冷えていく。
さっさと答えてしまった方が億倍マシでした。
「そのキスマークって」
「席座れー。テスト配るぞ」
神様のようにタイミングよく担任が入ってきました。
嫌そうな不満が溢れて、張り詰めていた空気がぶわりとほぐれていく。
ただ、高水だけは確信を得たいと睨みつけてくる。
「錦先輩の?」
さっきの言葉を上の句とした質問に、顔が熱くなる。それはもうイエスと同義だったのでしょう。彼女の顔は疑念と好奇心と多少の怒りをかき混ぜて、担任の言葉に渋々と席に戻っていった。
ぺらりと回された紙を手のひらで撫でつけて机に広げる。
心臓は後夜祭のように余韻で鳴り響き、これから起こるであろう嵐に備えろと全身に熱い血をポンプで送り続けている。
どうして。
友達作りに焦らなければ、痕が消えて誤魔化せたでしょうか。
私に表情管理の才能があったなら、バレることはなかったでしょうか。
シャーペンを走らせながら、いつもより溢れてくる唾液を飲み下す。
カリカリとした音が無数にぶつかり合う無言の教室で、視線の束がまた自分に突き刺さってきているような感覚に襲われる。
そんなはずないのに。
担任が手を叩いてプリントが回収される。
ホームルームが終わると、名前が呼ばれた。
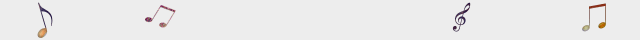
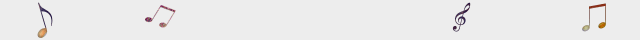
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


