 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
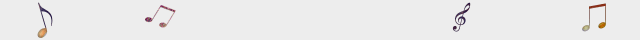
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
もうLOVEっ!ハニー!
第21章 眩さから逃げ出して
もう二度と私に関心なんて向かなくていいのに。
「さっきの話だけど、一瞬ついてきてくれる?」
絶対に数秒で終わるはずのない話なのに、四人の彼女らは廊下に出るよう言いました。
屋上に続く階段の前で立ち止まり、円のように囲まれる。
「え、マジなの」
「松園さんが?」
「信じらんない」
好き勝手な言葉の連打に黙って向かい合う。
黒い長髪をハーフアップにした高水は、クラスの中でも後ろから三番目に背が高く、目の前に立たれるとまるでこばるさんと話しているような視線の差でした。
言葉を探すように瞬きを数度してから、口を開く。
「いくらなんでも先ほどのは無粋すぎませんか」
「首元見たこと? それはごめんね。ちらって見えたからさ」
さらりと謝罪が出てきたので、それ以上続けられません。
「え、あのさあ」
次に出てくる射撃がどのような言葉なのか、頼んでもいないのに脳内で推察会議が始まります。
不釣り合いだと思わないの。
どうやって騙したの。
嘘ならもっとまともにつけないの。
あんな大会中にアピールして恥ずかしくないの。
一体どれが一番近い答えなのでしょう。
「どっちからなのか聞いてもいい?」
おや、予想外でした。
彼女の言葉に一切の棘はなく、純粋な興味が投げられる。背中の遠く後ろで談笑する同級生たちの声がさざ波となって鼓膜を震わせている。彼女らの視線は答えを待つように唇に集まっている。
「えっと、それはどちらから告白をという質問ですよね」
ふわっと笑いの風が吹く。
「あったりまえじゃん! 松園さん恋話したことないの?」
ないですよ。
高水がおかしいとばかりに手をぱたつかせて続ける。
「あのね、バスケ部女子は何人も錦先輩に振られてるんだけど、純粋にファンが多いの。付き合いたいっていうよりも拝んでたいっていうか、そういう存在じゃん、あの人」
同じ部活で見てきたからこその距離感の呼称に胸がドキッとする。
それは知らない立場のお話。
「だって二人きりで何話したらいいかも思いつかないもんね」
「わかる」
「あれはもう神様」
そこでつられて笑いがこみ上げてしまう。
だって、それはそれは本当にそうだから。
彼女らも共感に賛同するように笑う。
「だからさっきやっちんから聞いて、すっごい気になったの!」
高水弥生、でしたか。
そうでした。
「聞かせてよ」
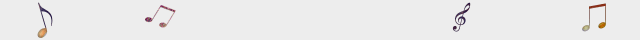
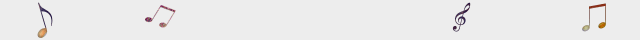
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


