 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
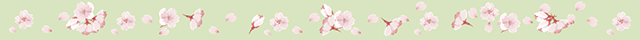
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
狼に囚われた姫君の閨房録
第37章 鶴ヶ城の悲劇(前編)
「殿、すみれ姫をご案内しました」
容保様の寝所である。太刀持ちの小姓が呼びかけ、襖をすっと開けた。
容保様は灯りも付けずに、窓から夜空を眺めていた。
「ご苦労。下がって休め」
小姓が一礼して下がると、容保さまは私を手招いた。
「こちらに来い。月はないが、星空が美しい」
私が膝をそろえて座ると、容保様は私の肩を抱いた。
「土方のことは聞いたな?」
「……はい」
宇都宮で重傷を負った歳三は、温泉地で静養しながら蝦夷(北海道)に向かったという。
「あのバカ、会津で戦うと言いやがった。『お荷物は引っ込んでろ』と言ってやったら大人しく湯治に行ったぜ」
「主計くんと利三郎くんも一緒にですか?」
「目付け役に同行させた」
「ありがとう存じます」
歳三のことだ。監視役がいなかったら、どんな無茶もしかねない。
「斎藤と……鈴木三樹三郎とかいったか?二人はどうしている?」
「ご重役方と軍議中でございます。鶴ヶ城だけは落とすわけにはいかぬと」
「鈴木三樹三郎もか?」
「ええ」
「あの者は新選組が粛清した伊東の弟なのだろう?いつから、味方になった?」
「実を言いますと……」
私は歳三の思惑を話した。
歳三が伊東甲子太郎を入隊させた理由は弟の三樹三郎にあること。三樹三郎はなんらかの鍵を握る人物だろうということ。
「なるほど、鈴木三樹三郎を死なせられない理由があったのか。土方にしては手ぬるいと思っていたが」
容保様は私の顎を掴んで仰向けた。容保様の唇が私のそれに吸い付いた。
「それにしても、鍵とはどういうことだ?あの者は、何をなすというのだ?」
私は首を振るしかなかった。
容保様の寝所である。太刀持ちの小姓が呼びかけ、襖をすっと開けた。
容保様は灯りも付けずに、窓から夜空を眺めていた。
「ご苦労。下がって休め」
小姓が一礼して下がると、容保さまは私を手招いた。
「こちらに来い。月はないが、星空が美しい」
私が膝をそろえて座ると、容保様は私の肩を抱いた。
「土方のことは聞いたな?」
「……はい」
宇都宮で重傷を負った歳三は、温泉地で静養しながら蝦夷(北海道)に向かったという。
「あのバカ、会津で戦うと言いやがった。『お荷物は引っ込んでろ』と言ってやったら大人しく湯治に行ったぜ」
「主計くんと利三郎くんも一緒にですか?」
「目付け役に同行させた」
「ありがとう存じます」
歳三のことだ。監視役がいなかったら、どんな無茶もしかねない。
「斎藤と……鈴木三樹三郎とかいったか?二人はどうしている?」
「ご重役方と軍議中でございます。鶴ヶ城だけは落とすわけにはいかぬと」
「鈴木三樹三郎もか?」
「ええ」
「あの者は新選組が粛清した伊東の弟なのだろう?いつから、味方になった?」
「実を言いますと……」
私は歳三の思惑を話した。
歳三が伊東甲子太郎を入隊させた理由は弟の三樹三郎にあること。三樹三郎はなんらかの鍵を握る人物だろうということ。
「なるほど、鈴木三樹三郎を死なせられない理由があったのか。土方にしては手ぬるいと思っていたが」
容保様は私の顎を掴んで仰向けた。容保様の唇が私のそれに吸い付いた。
「それにしても、鍵とはどういうことだ?あの者は、何をなすというのだ?」
私は首を振るしかなかった。
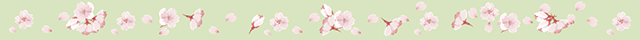
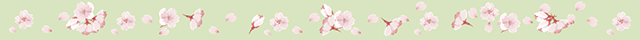
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


