 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
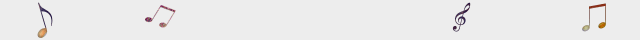
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
【SS】目が覚めたら…?
第25章 【ファン感謝】白雪姫 ①猟師(ハル)
あたしは返事をせずに、ハルの胸倉掴んで引き寄せて、頬にキスをした。
唇を合わせなくなってどれくらい経っているのか数えたことはないけれど、あたしからハルの頬にするキスは初めてのものだった。
唇が感じた…久しぶりで、そして最後になるハルの感触に、目頭が熱くなって鼻の奥がつんとなり、思わず泣きそうになった。
それをぐっと堪えて、精一杯の笑顔を作る。
「いってらっしゃいのご挨拶。たまにはいいでしょう、こういうの」
やはりハルから返るものはなく――。
最後はあたしから一方的で終わってしまった。
頬に手を添えて固まるハルは、なにを思っているのだろうか。嫌悪感を抱いていたら立ち直れないと思いながら、大きいその背中を後ろから両手で押して小屋から出すと、内側からドアを閉めた。
「ひっく……」
嗚咽があたしから漏れた。
あたしはドアに背を凭れさせたまま、ずるずると床に崩れ落ちる。
ぽたぽたと床を濡らすのは、あたしの涙。
お別れだ。
そう思うと哀しくてたまらない。
涙が止らず泣きじゃくる。
もう二度とハルに会うことはない。
もう二度とハルと笑い合うことはない。
もう二度とハルと熱を分かちあうこともない。
傍若無人であたしをすぐに従え、世間知らずのあたしが自活出来るまでの体力と知識をくれたひと……。
城から出たあたしに事情を聞かずに、夜中もずっと抱きしめて、あたしを孤独にさせなかったひと……。
王女扱いしないくせに、あたしを女として扱おうとして、ドレスも与えて、あたしに王女としてのプライドを満たせてくれたひと……。
今思えば、きっとハルがしてくれたことは、わかりにくい"優しさ"。
……そう、よく思ってみることにする。
いつの間にかあたしは、城の生活を忘れていた。
退屈で味気なく、そして居場所がなく追い出されたあの城の思い出は、ハルと出会うためにあったのだと、そう思えるほどに。
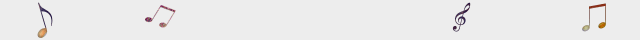
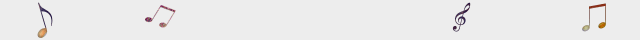
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


