 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
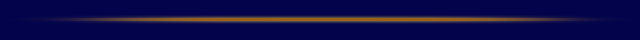
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
夢見桜~ゆめみざくら~
第3章 夜の哀しみ
一馬の存在と仏をつくり続けることがなければ、吟は真に狂っていたに相違ない。長い間、自分を縛(いまし)めていた鎖から解き放たれた今、吟は恐る恐る口を動かした。
「一馬さま」
それは、まるで言葉を覚え始めたばかりの幼子が喋るような、たどたどしいものではあったけれど、吟にもそして一馬にも何より確かな響きを持っているように思えた。
「一馬さま」
吟はもう一度、一馬の名を呼んだ。今度は噛みしめるように、ゆっくりと。
「お吟、今一度、俺の名を呼んでくれ」
「一馬―さま」
吟が繰り返すと、一馬の眼から一筋の涙が流れ落ちた。
吟は改めて桜の樹を見つめる。本当に葉の茂り方、枝の張り具合、何から何まであの寺の夢見桜に似ていた。
光円は今も元気で暮らしているだろうか。 吟の瞼にかつての師匠の慈愛に満ちた微笑が浮かび、消えていった。
だが、吟の帰る場所は、もうあそこにはない。何故なら、吟はこの男の、一馬の側で生きてゆくと決めたのだから。
「私を一馬さまのお側に置いて頂けますか」
吟の口から出た言葉を、一馬は信じられないことでも聞いたような表情で聞いた。
「俺を許してくれるというのか、お吟」
吟はゆっくりと頷いた。確かに力でお吟を欲しいままにする一馬を憎んだこともあった。けれど。声を失い、身体だけでなく心まで傷ついて出口の見えない暗闇をさまよっている時、いつも一馬が側にいてくれた。一馬が途中で見放したりせずに手を差し伸べ続けてくれたからこそ、こうして声を取り戻し、陽の当たる場所に戻ってくることができた。
一度は兄とも慕ったひとであった。
憎めるはずがない。
「一馬さま」
それは、まるで言葉を覚え始めたばかりの幼子が喋るような、たどたどしいものではあったけれど、吟にもそして一馬にも何より確かな響きを持っているように思えた。
「一馬さま」
吟はもう一度、一馬の名を呼んだ。今度は噛みしめるように、ゆっくりと。
「お吟、今一度、俺の名を呼んでくれ」
「一馬―さま」
吟が繰り返すと、一馬の眼から一筋の涙が流れ落ちた。
吟は改めて桜の樹を見つめる。本当に葉の茂り方、枝の張り具合、何から何まであの寺の夢見桜に似ていた。
光円は今も元気で暮らしているだろうか。 吟の瞼にかつての師匠の慈愛に満ちた微笑が浮かび、消えていった。
だが、吟の帰る場所は、もうあそこにはない。何故なら、吟はこの男の、一馬の側で生きてゆくと決めたのだから。
「私を一馬さまのお側に置いて頂けますか」
吟の口から出た言葉を、一馬は信じられないことでも聞いたような表情で聞いた。
「俺を許してくれるというのか、お吟」
吟はゆっくりと頷いた。確かに力でお吟を欲しいままにする一馬を憎んだこともあった。けれど。声を失い、身体だけでなく心まで傷ついて出口の見えない暗闇をさまよっている時、いつも一馬が側にいてくれた。一馬が途中で見放したりせずに手を差し伸べ続けてくれたからこそ、こうして声を取り戻し、陽の当たる場所に戻ってくることができた。
一度は兄とも慕ったひとであった。
憎めるはずがない。
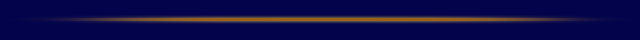
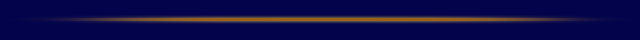
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


