 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
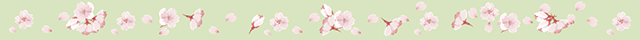
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
いつかの春に君と
第4章 君が桜のとき
今日は仲見世にほど近いこじんまりしたカフェで稽古が終わるまでの時間を過ごした。
相変わらず小春と向かい合うと緊張して言葉少なになってしまう。
いや、小春と同じで空間にいることが現実とは思えないのだ。
十二の年まで小春と常に肩を寄せ合いながら、生きて来た。
孤児院では母を恋しがって泣く小春が不憫で、抱きしめて寝かしつけた。
「泣くな、小春。にいちゃんがずっとそばにいるから…」
小春は鬼塚にしがみつくようにして眠りに就いた。
小春の甘い髪の香りを嗅ぎながら、いつしか鬼塚も眠りに就いた。
小春は自分の身体の一部のような気がしていた。
…だから、あの忌まわしい事件以来、小春と離れ離れになり、その身体の一部…いや、魂の半分を奪われたような喪失感を覚えてきたのだ。
その喪失感にはなかなか慣れることはできなかった。
小春が優しく裕福な里親に引き取られ、幸せな生活をしていると知らされて、ようやく諦めがついたのだ。
…だから、こんな風に目の前で微笑まれると、どうして良いか分からなくなる。
「徹さん、何を召し上がる?甘いものはお好きかしら?」
品書きを手に美しい瞳を無邪気にきらきらと輝かせる。
「…俺は珈琲でいい。あんたは好きなのを食べろ」
照れ臭くてついぶっきらぼうな言い方をしてしまう。
しかし小春は気にした様子もなく、じゃあ…と、少し恥ずかしそうに
「珈琲と紅茶と…それから…アイスクリームをください」
と、注文を取りに来た女給に告げた。
鬼塚は思わず尋ね返した。
「アイスクリーム…。好きなのか?」
…昔、まだ田舎に住んでいる頃、友達がくれた雑誌にアイスクリームの写真が載っていた。
小春は大きな眼を輝かせ、鬼塚に聞いた。
「にいちゃん、あいすくりーむて、なに?」
「…冷たくて甘い西洋のお菓子だ」
驚いたように眼を見開き、まじまじと写真を見つめる。
「つめたくてあまいん?たべるととけるん?」
「…うん。そうみたいだな」
…お菓子はおろか、日々の食事も満足に摂れないようは貧しい家だった。
小春はその味も想像できなかったことだろう。
切なくなった鬼塚は小春を膝に乗せ、言い聞かせるように答えた。
「…小春、にいちゃんがでかくなったら、お前にアイスクリームを食わせてやる。たくさんたくさん食わせてやる」
「ほんまに?」
小春は嬉しそうに笑い、鬼塚の首すじに抱きついてきた…。
相変わらず小春と向かい合うと緊張して言葉少なになってしまう。
いや、小春と同じで空間にいることが現実とは思えないのだ。
十二の年まで小春と常に肩を寄せ合いながら、生きて来た。
孤児院では母を恋しがって泣く小春が不憫で、抱きしめて寝かしつけた。
「泣くな、小春。にいちゃんがずっとそばにいるから…」
小春は鬼塚にしがみつくようにして眠りに就いた。
小春の甘い髪の香りを嗅ぎながら、いつしか鬼塚も眠りに就いた。
小春は自分の身体の一部のような気がしていた。
…だから、あの忌まわしい事件以来、小春と離れ離れになり、その身体の一部…いや、魂の半分を奪われたような喪失感を覚えてきたのだ。
その喪失感にはなかなか慣れることはできなかった。
小春が優しく裕福な里親に引き取られ、幸せな生活をしていると知らされて、ようやく諦めがついたのだ。
…だから、こんな風に目の前で微笑まれると、どうして良いか分からなくなる。
「徹さん、何を召し上がる?甘いものはお好きかしら?」
品書きを手に美しい瞳を無邪気にきらきらと輝かせる。
「…俺は珈琲でいい。あんたは好きなのを食べろ」
照れ臭くてついぶっきらぼうな言い方をしてしまう。
しかし小春は気にした様子もなく、じゃあ…と、少し恥ずかしそうに
「珈琲と紅茶と…それから…アイスクリームをください」
と、注文を取りに来た女給に告げた。
鬼塚は思わず尋ね返した。
「アイスクリーム…。好きなのか?」
…昔、まだ田舎に住んでいる頃、友達がくれた雑誌にアイスクリームの写真が載っていた。
小春は大きな眼を輝かせ、鬼塚に聞いた。
「にいちゃん、あいすくりーむて、なに?」
「…冷たくて甘い西洋のお菓子だ」
驚いたように眼を見開き、まじまじと写真を見つめる。
「つめたくてあまいん?たべるととけるん?」
「…うん。そうみたいだな」
…お菓子はおろか、日々の食事も満足に摂れないようは貧しい家だった。
小春はその味も想像できなかったことだろう。
切なくなった鬼塚は小春を膝に乗せ、言い聞かせるように答えた。
「…小春、にいちゃんがでかくなったら、お前にアイスクリームを食わせてやる。たくさんたくさん食わせてやる」
「ほんまに?」
小春は嬉しそうに笑い、鬼塚の首すじに抱きついてきた…。
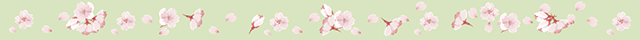
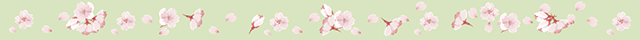
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


