 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
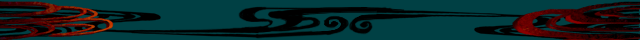
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
戦場に響く鈴の音
第26章 軍議
雪南のように瞑想だの心の鍛錬だのが器用に出来る男にはなれないとわかってる。
気に入らなきゃキレるし、直ぐに刀を抜いちまう。
神経が尖れば尖るほどそいつが酷くなるからと、独りになれる道場へ来た。
真っ暗な道場の屋根に雪が積もり、中は完全に冷え切ってる。
その真ん中まで行き、開き直ったように胡座をかき目を閉じる。
耳だけを澄ます。
降り積もる雪の音まで聞き取れるほどまで自分の感覚を細部まで研ぎ澄ます。
聴覚の次が視覚…。
暗闇でも全てが見えるまで目を凝らす。
そうやって自分の指の一本までを完璧に扱えるように全神経を集中させる。
ゆっくりと立ち上がり、手の平を握る。
手の中には存在しない双刃刀を感じる。
初めて羽多野から、あれの使い方を教わった時に言われた事は一つだけ…。
『身体の一部として扱いなされ…。』
普通の刀とは違う。
双刃刀は全身を使う。
無闇に振るえば刃の勢いが止まらず、使い手の手足までもをもぎ取ろうとする鬼切の刃だ。
脇で勢いを止め、肩で振るいを加速する。
その動きを覚える為に、古舞踊の型を身体に叩き込み、四六時中、双刃刀を手に布で巻き付けて生活した。
だから、あれが無くとも俺の身体に染み付いた感覚が俺に双刃刀を握らせる。
見えない双刃刀をゆっくりと振りかざしては脇で止め、肩から回して振り落とす。
手に伝わるは人を切る肉の感覚…。
目に映るは塵のように消える人影…。
戦場での経験を体感で隅々まで再現する。
そして、高揚が始まる。
女を抱いた時のように、それが快感へと変わってく。
全身が熱く、息苦しいのに身震いするほどの快楽が襲って来る。
快感に溺れそうになる俺を見る虎がニヤリと笑う。
油断などすれば俺を噛み殺すぞと、咆哮を上げる。
「切ってやるから、来いよ。」
あれは俺の中の鬼だ。
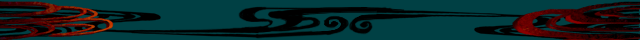
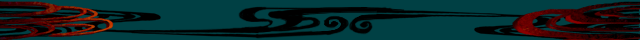
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


