 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
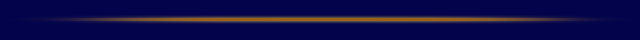
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
いまやめないで このままでいて
第5章 第5話 過ぎた日の思い出を彼にあずけて
坂田は本社のある東京の飯田橋に毎週月曜日、赴任先の北関東支店の借上げ社宅から出社する。
社宅といっても、単身赴任者用の小さな賃貸マンションで、妻と2人の子供がいる自宅は横浜にあった。
コンパクトなワンルームマンションでの2年目の生活に不自由はないばかりか、ひとりでいることの気楽さがむしろ楽しかったし、最寄り駅まではバスもあったが、本社出社の月曜日には電車が空いている早朝にのんびりと歩いて駅まで向かうことのほうが多かった。
空梅雨の6月も終わりに近づいたその月曜日の朝も、6時前にいつもどおり彼はマンションを出て駅へ歩いて向かっていた。
冬だとまだ明けやらない時間帯だが、朝日はもう眼の高さより上にまで昇っている夏至の頃ともなると日陰のほうが歩きやすいので、バス通りから1本裏の住宅道を歩く。
そのとき少し前のほうを白い子犬を連れて散歩している女の姿が見えた。
つば広の黒いサンハット…
彼は忘れかけていた花屋でのことを思い出した。
(そうだ、あのときの人だ)
それは、1か月ほど前の朝、その道を通って駅に向かっていた時のことだった。
小さな交差点を越えようとしたとき、足元に飛び出してきたものと彼はぶつかりそうになった。
「あっ! すみません!」
ぶつかりそうになった白い小さなプードルとほとんど同時に黒のサンハットを被った女が小さく叫んで彼に謝った。
「ごめんなさい」
リードを引いて犬を抱きかかえ、顔を上げてもう一度彼に詫びた彼女のグレーの縁の眼鏡とえくぼが、なぜかそのとき坂田の印象に強く残ったのだった。
子犬連れの彼女はそれからすぐに交差点を曲がり、彼がそこに着いた時にはもうその姿は見えなくなっていた。
(この時間が彼女の散歩のときなんだ…)
ほんのわずかだったが彼の口元が緩んだ。
始発駅に近い朝の中距離電車は空いている。
それでも坂田はほとんど空席のグリーン車を使い、前夜に買っておいたサンドイッチとコーヒーの朝食を摂るのが毎週の楽しみのひとつだった。
車窓を流れていくそれぞれの街の景色を眺めながら人混みの都心へ入り、会社へは8時前に着くことができる。
今朝見かけた彼女のことを思い出しながら、彼は束の間の穏やかなひとときを過ごす1日の始まりだった。
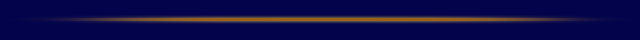
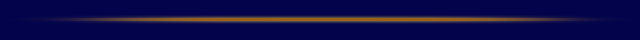
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


