 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
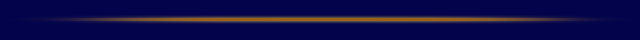
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
いまやめないで このままでいて
第5章 第5話 過ぎた日の思い出を彼にあずけて
東京の立川にある昭和記念公園は秋になると広大なコスモス畑が広がる。
平日にもかかわらず、その淡い色が高い蒼空に映えて揺れるお花畑に人の姿は多かった。
「来られたことありますか?」
「ずっと昔に一度… 主人と来たことがありますけど…」
花にはあまり関心のない夫は早く帰りたがったので、楽しめなかったという佳緒里を見て、ここを選んでよかったと坂田は思った。
「車で来れば連れて来れましたね」
犬連れの客を見て、彼は佳緒里の顔を見ながら言うと、
「ちゃんとお留守番してくれてますから」
佳緒里も坂田の眼を見て微笑みながら応える。
都心の本社へ出社する月曜日の朝、犬を散歩させる佳緒里とほんのわずかな時間、待ち合わせして立ち話をするようになった坂田は頭に占める彼女の領域が日々大きくなっていた。
そしてそれは佳緒里も同じだった。
白いプードルの子犬を抱いて、目立たないように彼と短い会話を交わすことが毎日の糧となっていたのである。
まだ40半ばを過ぎたばかりの自分を気遣って、亡夫の両親は籍を抜いて新しい伴侶を見つけるように勧めてくれるのだが、今はまだそんなことをする気持ちにはなれないという佳緒里の律義さが坂田には少し不憫に思えた。
「夫のことを思うわけではないのですが…」
「ご両親のことを思うんですね?」
「はい…」
芝生に腰を下ろして、揺れるコスモスを眺めながら彼女が小さくうなずく。
「それに…」
「え?」
「あの家に夜ひとりでいるのが怖いんです…」
坂田は思わず隣にいる佳緒里の横顔を振り向いた。
「それじゃ、夜怖くなったら電話ください」
「え?」
今度は佳緒里が振り向く番だった。
「そんなご迷惑…」
「迷惑なんかじゃないですよ。
さすがに泊りには行けませんけど…」
泊りには行けないという坂田のことばで佳緒里は小さく笑った。
「そう言っていただけるだけでうれしいです」
今夜からでもどうぞ、と言う坂田の眼を見ながら佳緒里が頭を下げ、彼は笑みを返した。
「お茶でもしに行きましょうか」
「はい」
先に立った坂田に自然と手をつながれて佳緒里が立ち上がろうとして膝を寄せたとき、不意に吹いた風にあおられたスカートの中の刺繡の入った白い下着が彼の眼に焼き付いた。
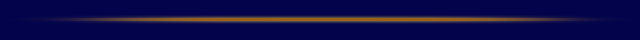
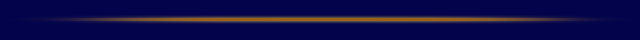
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


