 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
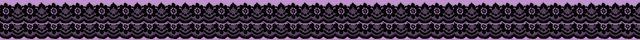
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
Only you……番外編
第6章 目眩
それから毎日、わが社へ透真はやって来た。目的は例外なく伯父への抗議だった。毎日毎日、「なぜ次期社長が僕ではないのだ!」と文句を言いに来たのだ。
そして帰り際には私を汚いものを見るような目で見ていく。初めは驚きのあまり大して意識していなかったが、だんだんと悲しくなってきた。私が悪いわけではないと、言い聞かせても、心のどこかでは“お前なんかがいるからだ”という声が聞こえてきた。耳をふさいでもその声は消えることなく、私は追い詰められていった。それは他の誰にでもなく、私自身によって。
ある日私は伯父に向こうの社へ行く仕事を命じられた。私は自動車の免許を持っていないので、タクシーを呼び1時間かけて行く。本来ならば30分くらいで着くはずの距離ではあるが、今の時間は渋滞が酷く2倍もの時間がかかってしまうのだ。
会社へ着くと真っ先に社長室へと向かう。息子ということで、無条件に会社は透真に任せられたらしい。透真は大学まできちんと出ていて、会社に実際勤務した期間は、実は結構短いらしい。それ故に、至らない点が多いらしく、社内は混乱していた。
“社長室”と書かれた部屋をノックすると、数秒置いて「はい」という声が聞こえた。それを合図に私は大きな黒い扉を開けた。
私が中に入っても、透真は机に向かったまま顔を上げようとはしなかった。
「あの……」
私が声をかけて初めて上げた顔には、明らかに嫌悪感が浮かんでいた。そのあまりに濃い不快の色に私の心臓がキリッっと痛む。最近多い痛みだった。昔は今よりも酷かった痛みに、私の顔を歪む。
「何しに来た」
私を睨んだまま、冷え切った声で問い詰めるように言う。
「合併についての書類と、詳細説明をしに――」
私が話している途中で、透真は立ち上がり、入り口に立ちすくんでいる私に詰め寄った。
「帰ってくれ。そんな話聞きたくない」
肩を強く押し、そのまま私を追い出そうとする、一応は抵抗してみるものの、その力の強さに驚くほうが大きかった。
「聞いてくれなきゃ困るっ」
「お前が困ろうが僕は知らない」
ナイフのように鋭く尖った言葉が私の胸に突き刺さる。
――苦しい……。
「とにかくもう来ないでくれ」
さらに浴びせられる言葉は、次々と突き刺さり、更なる痛みを生んでゆく。
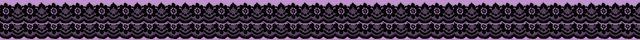
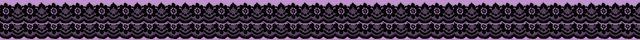
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


