 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
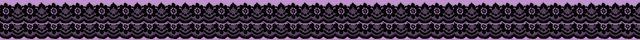
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
Only you……番外編
第3章 昼休みは
大慌てでシャワールームから出てきた社長――佐伯 貴正――に、僕――東 透真――は朝食用のパンを持たせ、車に乗り込んだ。車という狭い密室に入ると、貴正のシャンプーの香りが漂いくすぐったかった。僕がくすりと笑うと、貴正が怒ったように「何?」と尋ねてきた。けど、教えてやんねー。
貴正のマンションから会社までは結構近い。それは社長が寝坊の常習犯だから、少しでも遅くまで寝ていられるようにとの配慮から、僕がこの場所を選んだからだ。――しかし、僕と貴正は同棲しているわけではない。僕は貴正と結ばれてからも実家に住んでいるし、貴正から一緒に住もうなどと言われたことも、言ったこともない。それは僕が実家に寝たきりの祖母と下半身の不自由な母をもっているからで、僕がいないと困るからだ。父はすでに他界していた。
「はい。着きましたよ」
「んー」
サンドウィッチをくわえたまま、鼻で返事をすると、貴正は鞄を持って車を降りた。僕もそれに続く。
ここからは――会社に入ってしまえば、僕は貴正を社長と呼ばなくてはならない。それが僕は嫌だった。なんだか2人の間に距離ができてしまうみたいで。
「おはようございます、社長」
渥美 りん(あつみ りん)さんが声をかけてくる。彼女は副社長であり、社長の養子――といっても実際は養子縁組などにはなっていない――架上 麻都(かがみ あさと)くんの秘書だった。
「おはよう、りん君。麻都はどうした?」
「副社長はもういらしてますよ。何だか今日は真面目にお仕事をしてくれるみたいで」
「ほう、それはなんとも私とは大違い」
貴正――あいや、社長は「ははっ」と笑った。それにつられて、僕と渥美さんも笑う。
「では、失礼します」
渥美さんは僕にも会釈すると、すたすたとその場を去っていった。彼女は社内での人気者で、憧れの眼差しを向けている社員も少なくない。その歩く姿は男の僕から見てもかっこよかった。
「いつまで見てるんだ?」
そう言われて、我に返ると社長が僕を睨んでいた。
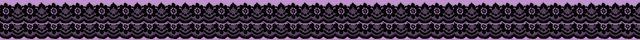
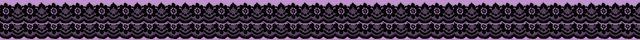
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


