 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
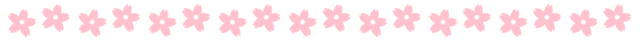
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
はなむぐり
第10章 花潜り
穏やかに時間が流れている。
朝食を食べ終えた蜜樹は兄に手を合わせてから、枕元に2杯目のカフェオレと私の辞書と数冊の小説を用意して寝ながら読んでいる。私はリビングでカフェオレを飲みながら、新聞を読んでいた。ふと兄に目を向けると、笑っているが日に当たって眩しそうにしているような表情に見え、カーテンを半分だけ閉めた。
台所に行ってカフェオレを作り、兄の前に置いた。甘い物が苦手だったかさえも分からないが、蜜樹が好きな飲み物なんだ。少しだけ、飲んでみてほしい。
「兄さん、いい子に育ったよ。これからも、父さん母さんと蜜樹を見守ってほしい」
兄さんと口にすると胸が熱くなるから言いたくない。だけど、今日はそう呼びたいんだ。父さん母さんと呼んでダメな息子に戻るように、私は未熟なままだ。手を合わせて礼をし、寝室に向かった。
すると、日の光を浴びながら、すやすやと仰向けで眠っている。枕元には開かれた辞書、手には二枚の赤い葉。昨日挟んだ赤い葉を眺めながら、眠ってしまったのだろう。手から赤い葉をそっと取って辞書に挟み、無防備な寝顔を見つめる。何か良い夢を見ているのか、頬笑んでいる。
「蜜樹…一生、愛すよ」
起きたらもう一度伝えると決めて、露わになっている太ももを撫でる。
「うっ…ん…」
パジャマの袖を口元に持っていき、赤子のように噛みながら感じている。撫で回しながら口づけを落とし、脚の間に座った。屈んでパジャマの裾をめくると、毛先についた蜜が日の光に当たってきらきらと光っている。花びらをめくり、顔を出した種は見つめるほど突き出てきて、熱い息を吐くと穴がきゅっと締まってぶわっと開き、白い蜜が滴り落ちる。
起きてしまうだろうか。
見上げると、無意識なのかパジャマのボタンを外している。
私の愛する人。
死んでも、愛してる。
この身体に私を刻み、生きている限り、蜜樹を離さない。
数え切れないほど舐めて吸って。
花は枯れるが、この花はずっと蜜を絶やさず溢れさせる。私を生かすために。
健気で愛しい花に口づけ、舌を沈ませた。
花が悦ぶ、一番弱いところにまで。
《終わり》
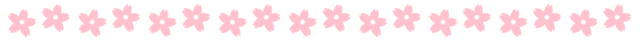
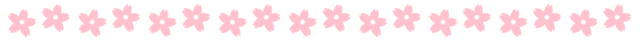
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


