 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
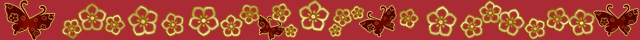
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
性神がこの世に放った獣たち~起
第1章 告白
私と妻は、私が三十妻が二十五の時に出会った。妻は私の恩師の娘で、恩師から妻を紹介された。見合いと言う形ではあったが、それを断ることなど私にはできなかった。断るということは自分の将来を断つことであり、恩師の娘を妻とすることだけが、私に与えられたただ一つの道だった。
今でも私は覚えている。お互い初めて顔を合わせた時だ。「初めまして五條創介です」と私が挨拶しても、妻は軽く頭を下げただけで名を名乗ることすらしなかった。席に着いた後、私は妻の冷たい視線を感じた。値踏みをするような妻の酷薄の眼に、私は絶望した。私はこの女と結婚しなければ、私に未来はない。たとえ結婚したとしても、私はこの女と生涯心を通い合わせることなどないだろう。
二つの選択肢? 冗談じゃない。私にはただ一つの答えしか許されていなかったのだ。
学者一家の一人娘として育てられた苦労知らずの妻は、奨学金で学生時代を過ごした私を何かにつけてバカにしてきた。自分はサラブレッドで、私は駄馬であると、私たちの息子と娘の前で子守歌のように言っていた。自分の父がいなければ、私は教授まで駆け上がることはできなかったと、私の陰でこそこそ話している。間違ってはいない。その通りだ。私は上に行くためにお前と結婚したのだ。お前を愛したことなど一度もないし、この先もお前に対する感情は変わらない。でもこれだけは覚えておけ。お前の父親の論文を書いたのは私で、私はお前の父親の雑用をすべて引き受けてきたのだ。お前の父親の功績はすべて俺が成したものだ。だから私は、今は亡きお前の父親の後を正々堂々と受け継ぐことができるのだ。
二十五年連れ添ってきたが、妻が変わることなど一度もなかった。そして私は気付いた。妻はサラブレッドなんかではなく、実に平凡な五十路の女だということを。
家の中で私だけ異物なのだ。所詮私は妻の家の血の継承だけに仕方なく選ばれた雄に過ぎない。都内にある家も妻の実家から援助してもらって購入している。夏の休みに向かう軽〇沢の別荘も妻の実家のものだ。子供二人を授かった時点で、私は用済みなのだ。
妻は私を捨てない代わりに、私を利用して生きている。ある時はメルセデスの運転手として、またある時は教授夫人と呼ばれるために。
辛うじて利用する価値があるから、妻は私と暮らしているのだ。
今でも私は覚えている。お互い初めて顔を合わせた時だ。「初めまして五條創介です」と私が挨拶しても、妻は軽く頭を下げただけで名を名乗ることすらしなかった。席に着いた後、私は妻の冷たい視線を感じた。値踏みをするような妻の酷薄の眼に、私は絶望した。私はこの女と結婚しなければ、私に未来はない。たとえ結婚したとしても、私はこの女と生涯心を通い合わせることなどないだろう。
二つの選択肢? 冗談じゃない。私にはただ一つの答えしか許されていなかったのだ。
学者一家の一人娘として育てられた苦労知らずの妻は、奨学金で学生時代を過ごした私を何かにつけてバカにしてきた。自分はサラブレッドで、私は駄馬であると、私たちの息子と娘の前で子守歌のように言っていた。自分の父がいなければ、私は教授まで駆け上がることはできなかったと、私の陰でこそこそ話している。間違ってはいない。その通りだ。私は上に行くためにお前と結婚したのだ。お前を愛したことなど一度もないし、この先もお前に対する感情は変わらない。でもこれだけは覚えておけ。お前の父親の論文を書いたのは私で、私はお前の父親の雑用をすべて引き受けてきたのだ。お前の父親の功績はすべて俺が成したものだ。だから私は、今は亡きお前の父親の後を正々堂々と受け継ぐことができるのだ。
二十五年連れ添ってきたが、妻が変わることなど一度もなかった。そして私は気付いた。妻はサラブレッドなんかではなく、実に平凡な五十路の女だということを。
家の中で私だけ異物なのだ。所詮私は妻の家の血の継承だけに仕方なく選ばれた雄に過ぎない。都内にある家も妻の実家から援助してもらって購入している。夏の休みに向かう軽〇沢の別荘も妻の実家のものだ。子供二人を授かった時点で、私は用済みなのだ。
妻は私を捨てない代わりに、私を利用して生きている。ある時はメルセデスの運転手として、またある時は教授夫人と呼ばれるために。
辛うじて利用する価値があるから、妻は私と暮らしているのだ。
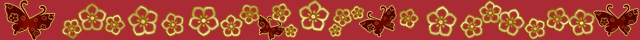
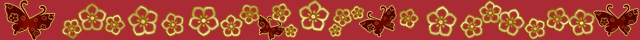
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


