 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
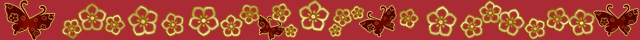
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
空蝉
第6章 臥待月
臥待月の 昇る頃
薄衣ひとつ やわ肌に 纏いて、待てば 葉擦れにも
もしやと思い ときめいて
夜露をしらぬ このからだ いつしか濡れて なおさらに
恥じらう肌の 匂いたつ
臥待月に 照らされて ひと夜の夢に わけ入れば
手折りし人の 指先に 花は、淫らに 咲き狂い
刹那に散るも さだめとて
快楽(けらく)の波の さらうまま 昇って、堕ちて 砕け散る
臥待月を 待ちわびた 身には、逢瀬の とき、早く
過ぎて、夜明けを 待つことも なく、帰る背の つれなさに
名残の痕も 残り香も すべてが辛く ただ、ひとり
女のままで 泣き濡れる
臥待月は 隠れても 妖しき花ぞ 咲き匂う
身をもてあまし 明け風に 火照る乳房を 醒まさんと
窓辺に待てば 仄暗い 鬼女の面(おもて)と 見紛える
魔性の笑みの 浮かびくる
臥待月の 哀しさは 傀儡に堕ちた この肉か
それとも、濡れる 肉の花 咲かせた人の つれなさに
見しらぬひとに このからだ ゆだねようかと そう思う
傍から募る 恋しさか
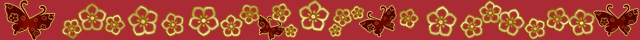
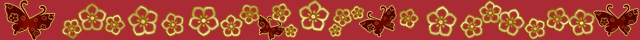
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


