 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
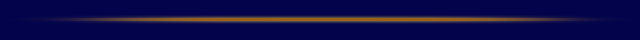
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
愛することで私たちは罪を犯す
第1章 1. 悲劇の序章
琉泉は孤児だ。
先々代である祖父 偀が、ある日突然連れてきた、細くて小さな女の子。
偀は、児童養護施設から虐待にも似た嫌がらせを受けていた琉泉を、養子として引き取ったのだと響の両親に説明した。
養育費をはじめとする琉泉にかかる全ての費用を自分がもつから、響と一緒に育てて欲しい、と。
娘がほしかった母 鈴音は喜んで承諾し、父も「鈴音と響が良いなら歓迎する」と柔軟だった。
響も一人っ子だったこともあり、妹ができるのは嬉しかった。
(結局、妹のように思ったことは一度もなかったけどな)
最初はとても仲がよく、琉泉は響の後をずっとついてくるような子だった。
そんな琉泉が、とても可愛かった。
だが、いつからか彼女は変わってしまった。
響を仕えるべき主人として、自分を使用人として、明らかな壁を作っている。
そもそも、偀が琉泉にボディーガードの仕事を与えたのは、琉泉が八神に対して引け目を感じないようにするためだ。
別に、今までの恩義から八神家のために尽くせ、という意味で与えた仕事ではない。
ボディーガードという内容も、身体を張って守れというわけではなく、ただ彼女に向いている仕事がそれだったというだけだ。
偀自身は彼女に他に就きたい仕事があるのなら、喜んでそれを応援すると前々から言っている。
恩返しのために生きるのではなく、自分のために生きるように。
それが、偀、もとい八神の願いだった。
だから、琉泉には自由を得る権利がある。
そしてそれを与えるのは他の誰でもなく響の役割だ。
自分に服従を誓うこの子を、「もう十分だ」と手放してやれば、琉泉は自由になれる。
たが、それを響はしない。
もし護衛の役を解いてしまったら、琉泉はもう側にはいてくれないかもしれない。
家もきっと出てしまうだろう。
自由になって欲しいと願う一方で、その願いを壊しているのも自分なのだ。
さっきも同僚の一ノ瀬と、何かアイコンタクトを取っていた。
やれやれ、とでも言うような一ノ瀬のあの態度が、妙に心をざわつかせる。
自分の知らない琉泉が増えていくことに、変な焦りを感じる。
「はぁ……」
手が届く距離にいるのに、手を伸ばすことができないのが辛い。
そんな感情を紛らわせるかのように、響は琉泉から目をそらし、窓の外を眺めていた。
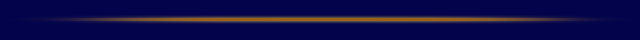
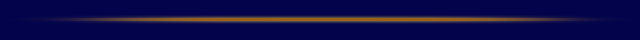
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


