 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
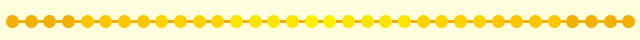
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
官能能力者 あおい
第33章 間章:折木さんの夏休み
どれだけ、そのままいただろう。
ぽつ・・・ぽつぽつ・・
大きな雨粒が私の頬に、服に落ちてくる。
それはすぐに大振りの雨になって地面を打つ。それでも、私は動けない。
起こったことが受け入れられない。
この世の現実の全てが、ずっとずっと遠くにいってしまったようだった。
雨粒が頬を伝って、唇を濡らす。私のなけなしの体温を灰色の雨が奪っていく。
凍える感覚もないまま、私はただ冷えていく。
そのとき、ふと、思い出した。
『身体を大事にしなきゃ』
ああ、そう言っていた人がいた。
そうか・・・
「身体を・・・大事にしなきゃ・・・」
誰にともなくつぶやくように言った。そして、やっときしむように身体が動き出す。
フラフラと雨の中を歩いた。
いったいどこに?わからない。
道が暗い。どこに行ったらいいのかわからない。
どうしていいかも、わからない。
ただ、ただ、足を動かす。
どれだけ歩いただろうか。
「折木さん!どうしたの!?」
びっくりしたように声をかけてきた誰か。
青色の傘をさした、高島あおいが、そこにいた。
☆☆☆
促されるままに、私は高島さんのお家にお邪魔することになった。
シャワーを浴びさせてもらい、着替えとして、新しい下着とスウェットの上下まで用意してもらった。
そして、今、私は高島さんの部屋で座って温かいココアを飲ませてもらっている。
ココアに溶けている糖分のおかげか、だいぶ気持ちが落ち着いた気がする。そして、さっきまでのぼんやりとした現実の認識が少しずつはっきりしてきた。
ああ・・・私は・・・。
思い出したくない言葉が頭をよぎりそうになり、ギュッとココアの入ったマグカップを握りしめる。高島さんはそんな私をそっとしておいてくれている。
ココアの残りが冷め始めた頃、やっと私は声が出るようになった。
「振られて・・・しまいました」
ポツリと言う。そんな事を言う必要はないのかもしれないが、珍しく、誰かに聞いてほしかったのかもしれない。
「・・・なんか、あったんだろうなって」
高島さんはそれだけ言った。沈黙が、心地よい。きっと、あれこれ聞かれたら、私は腹を立てて出ていってしまったかもしれない。
ぽつ・・・ぽつぽつ・・
大きな雨粒が私の頬に、服に落ちてくる。
それはすぐに大振りの雨になって地面を打つ。それでも、私は動けない。
起こったことが受け入れられない。
この世の現実の全てが、ずっとずっと遠くにいってしまったようだった。
雨粒が頬を伝って、唇を濡らす。私のなけなしの体温を灰色の雨が奪っていく。
凍える感覚もないまま、私はただ冷えていく。
そのとき、ふと、思い出した。
『身体を大事にしなきゃ』
ああ、そう言っていた人がいた。
そうか・・・
「身体を・・・大事にしなきゃ・・・」
誰にともなくつぶやくように言った。そして、やっときしむように身体が動き出す。
フラフラと雨の中を歩いた。
いったいどこに?わからない。
道が暗い。どこに行ったらいいのかわからない。
どうしていいかも、わからない。
ただ、ただ、足を動かす。
どれだけ歩いただろうか。
「折木さん!どうしたの!?」
びっくりしたように声をかけてきた誰か。
青色の傘をさした、高島あおいが、そこにいた。
☆☆☆
促されるままに、私は高島さんのお家にお邪魔することになった。
シャワーを浴びさせてもらい、着替えとして、新しい下着とスウェットの上下まで用意してもらった。
そして、今、私は高島さんの部屋で座って温かいココアを飲ませてもらっている。
ココアに溶けている糖分のおかげか、だいぶ気持ちが落ち着いた気がする。そして、さっきまでのぼんやりとした現実の認識が少しずつはっきりしてきた。
ああ・・・私は・・・。
思い出したくない言葉が頭をよぎりそうになり、ギュッとココアの入ったマグカップを握りしめる。高島さんはそんな私をそっとしておいてくれている。
ココアの残りが冷め始めた頃、やっと私は声が出るようになった。
「振られて・・・しまいました」
ポツリと言う。そんな事を言う必要はないのかもしれないが、珍しく、誰かに聞いてほしかったのかもしれない。
「・・・なんか、あったんだろうなって」
高島さんはそれだけ言った。沈黙が、心地よい。きっと、あれこれ聞かれたら、私は腹を立てて出ていってしまったかもしれない。
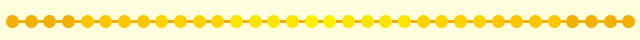
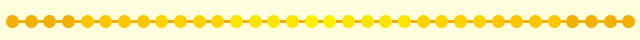
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


