 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
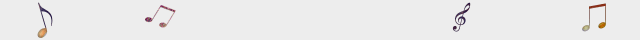
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
彼女はボクに発情しない
第20章 三日月が導く静かなる助奏
☆☆☆
暗い寝室に青色の街明かりが薄っすらと差している。
陽太と家の前で別れた後、私は着替えもせずにベッドに横になっていた。
陽太に、ブサイクな顔を見られてしまった。
あんなに涙が出てしまうなんて予想もしなかった。それに、本当は言いたいことも違った。
『陽太に謝りたい』
じゃなくて、『陽太が好き』って言いたかった。
でも、ダメだった。どうしても言えなかった。やっぱり陽太を目の前にすると、これまでの色々が思い出されて、『迷惑をかけている』『重荷になっている』という気持ちが先に立つ。
陽太には幸せになって欲しい。
いつもいつも、元気で優しくて、皆の人気者で、絶対に絶対に幸せになれる人だ。
私にずっと縛られていていい訳がない。
そう思うのだ。
思い切って、その気持ちを言葉にしたら、涙が止まらなくなってしまった。
自分で言ったくせに、陽太が、私を見捨ててどこかにいってしまうのではないかと、怖くなってしまった。
だから、陽太が『そんなことない』と言ってくれたときは、心底ホッとした。
あの三日月の下、私の額にキスをしてくれたときは、嬉しかった。それだけで、ぐちゃぐちゃに乱れた心がすーっと安定した。
いつもそうだ。ちゃんとしなきゃしなきゃと思っても、すぐにまた、私は陽太にすがりつきたくなってしまう。陽太を頼りにしてしまう。
陽太のそばにいると、それだけで深く深く安心する。陽太が守ってくれると実感する。帰りの電車の中も、じっと黙っていたけれど、気持ちは驚くほど落ち着いていた。
でも、今はまた怖い。心のなかから怖さがにじみ出てくる。
こんなに優しい人を、こんなにも大事な人を、私は苦しめているのではないかと、怖くて、怖くて、たまらなくなる。
『先にキスしてもらったほうが、陽太とお付き合いする権利を取る』
しかも、私は彼女にこう付け加えたのだ。『発情したときのキスは私もわけわかないでしちゃうときあるからノーカンで』と。
なんで、あんな勝負受けてしまったのだろう。確かに発情のドサクサで何度かキスをしたことがあったけど、普通の女の子のように、告白して、キスをしたことなんかない。それどころか手を繋いだこともない。
暗い寝室に青色の街明かりが薄っすらと差している。
陽太と家の前で別れた後、私は着替えもせずにベッドに横になっていた。
陽太に、ブサイクな顔を見られてしまった。
あんなに涙が出てしまうなんて予想もしなかった。それに、本当は言いたいことも違った。
『陽太に謝りたい』
じゃなくて、『陽太が好き』って言いたかった。
でも、ダメだった。どうしても言えなかった。やっぱり陽太を目の前にすると、これまでの色々が思い出されて、『迷惑をかけている』『重荷になっている』という気持ちが先に立つ。
陽太には幸せになって欲しい。
いつもいつも、元気で優しくて、皆の人気者で、絶対に絶対に幸せになれる人だ。
私にずっと縛られていていい訳がない。
そう思うのだ。
思い切って、その気持ちを言葉にしたら、涙が止まらなくなってしまった。
自分で言ったくせに、陽太が、私を見捨ててどこかにいってしまうのではないかと、怖くなってしまった。
だから、陽太が『そんなことない』と言ってくれたときは、心底ホッとした。
あの三日月の下、私の額にキスをしてくれたときは、嬉しかった。それだけで、ぐちゃぐちゃに乱れた心がすーっと安定した。
いつもそうだ。ちゃんとしなきゃしなきゃと思っても、すぐにまた、私は陽太にすがりつきたくなってしまう。陽太を頼りにしてしまう。
陽太のそばにいると、それだけで深く深く安心する。陽太が守ってくれると実感する。帰りの電車の中も、じっと黙っていたけれど、気持ちは驚くほど落ち着いていた。
でも、今はまた怖い。心のなかから怖さがにじみ出てくる。
こんなに優しい人を、こんなにも大事な人を、私は苦しめているのではないかと、怖くて、怖くて、たまらなくなる。
『先にキスしてもらったほうが、陽太とお付き合いする権利を取る』
しかも、私は彼女にこう付け加えたのだ。『発情したときのキスは私もわけわかないでしちゃうときあるからノーカンで』と。
なんで、あんな勝負受けてしまったのだろう。確かに発情のドサクサで何度かキスをしたことがあったけど、普通の女の子のように、告白して、キスをしたことなんかない。それどころか手を繋いだこともない。
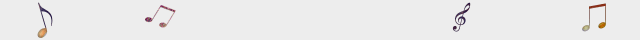
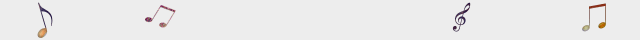
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


