 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
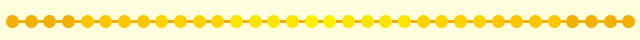
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
背徳は蜜の味
第34章 人妻その三十四
「もしかして…先生がお使いになっていた毛布では?」
「ええ、でも安心してください。多分綺麗だと思いますから」
「これを取ってしまったら先生の毛布がないんじゃありません?」
「僕は大丈夫、ほら、筋トレでもして身体を暖めますから」
「そんなのダメです!この毛布をお借りすることはできません!」
「弱ったなあ…受け取ってくださいよ
ここに泊まればいいって言い出したのは僕なんですから、あなたに風邪を引かせるわけにはいきませんよ」
じゃあ…
瞳は思い付いた大胆な事を提案してみた。
「ご一緒に…毛布にくるまりませんか?
あ、決していやらしい事をしようとか思っていないんです。ほら、雪山なんかでは抱き合ったほうが一番暖かくなるって言いますでしょ?」
「それはマズイんじゃないかなあ…
ほら、どちらにその気がなくても男と女だし…」
「今はそんなことを言ってる場合ではないですよ。
先生が言うように風邪を引いたらどうするんですか!」
そう言って、半ば強引に瞳は遠藤を毛布に引き入れた。
「本当だ…とても暖かいですね」
「でしょ?やっぱり最初からこうするべきだったんだわ」
瞳は忘れかけていた男の体臭に包まれて
いつの間にか甘えるように体を密着させていた。
「幼児用の枕じゃ小さすぎますね」
そう言うと遠藤は大胆にも瞳を腕枕してくれた。
久しぶりの腕枕…
何年ぶりだろう…
失くなった夫も、よくこうして腕枕してくれたっけ…
思い出すと体が疼いてくる。
『やだ、私ったら破廉恥なことを想像しちゃった!』
心の片隅に遠藤先生が狼に豹変して襲ってきたりして…
なんて考えると、体が火照ってきて、とてもじゃないが眠るどころか目が冴えてくる。
「香ちゃんのお母さん?
少し熱っぽいんじゃないですか?」
咄嗟に、いつも園児達にするように
遠藤はおでこを瞳のおでこにくっつけてきた。
「ほら、やっぱり熱い…毛布を持ってきたのが遅かったかな…風邪をひいてしまいましたか?」
おでこをくっつけたまま彼が喋るので
吐息がかかってますます体が火照ってくる。
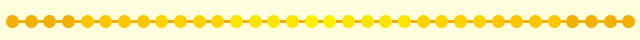
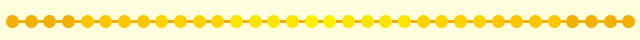
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


